ここで解説している国家試験の過去問は一般財団法人 動物看護師統一認定機構HPを参考にしていますので、各自で過去問内容を確認したうえでご覧ください。
今回は第1回愛玩動物看護師国家試験、一般問題の第11~20問の解説をしていきます。
問11 腎臓
問11 解説です↓
今回は腎臓について全体的に問われている問題ですね。この問題は少し難易度が高めですが、この年の必須問題でも似たような糸球体の問題が出ていますので、腎臓をしっかり学んできた方はあっさり2問とも解けたでしょう。他の人と差がつく問題ですね。
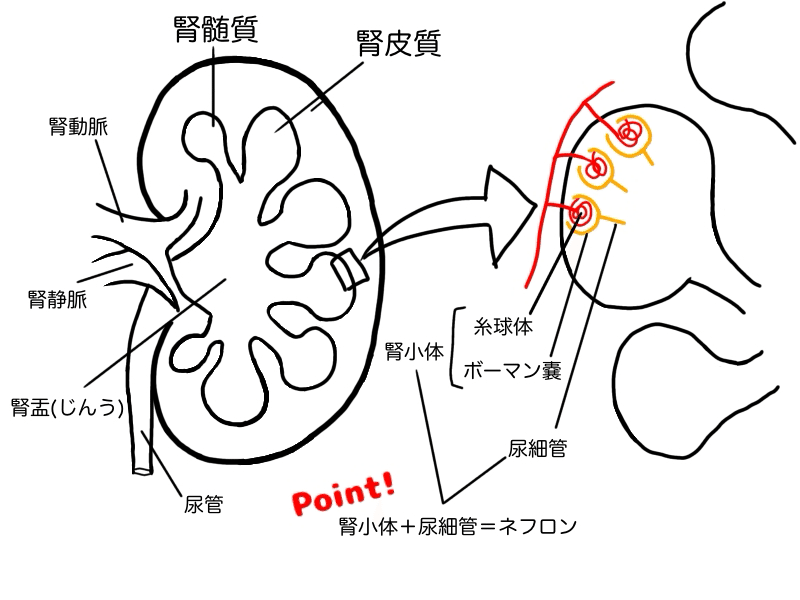
糸球体とボーマン嚢を合わせて腎小体。腎小体と尿細管を合わせてネフロン。
ここが混乱しやすいので出題されやすいです。
他の選択肢についても触れておくと
①⇒左が遊走腎。右側は左腎より頭側に固定されています
②⇒◎
③⇒腎門(そんなに大事な知識じゃない)
④⇒近位尿細管が約70%といわれる
⑤⇒逆。濃くなる
問12 脳神経
問12 解説です↓
こちらの問題も、この年の必須問題に関連した脳神経の問題が出ていました。脳神経は12個と決まっているので出しやすいのです。
脳神経について説明する前に、まずは選択肢にも一部出てきた「運動神経」「感覚神経」「交感神経」「副交感神経」についてみていきましょう。
| 神経の名前 | 何をする? | どこからどこへ? | いつ働く? |
|---|---|---|---|
| 感覚神経 | 「感じる」神経 | 体 ➡ 脳 | 何かを感じたとき (痛い、冷たいなど) |
| 運動神経 | 「動かす」神経 | 脳 ➡ 筋肉 | 動くとき (走る、話すなど) |
| 交感神経 | 「戦う・動く」神経 | 自律神経のひとつ | 緊張・ストレス・興奮時(ドキドキ、汗) |
| 副交感神経 | 「休む・リラックス」神経 | 自律神経のひとつ | おちついてる時・ 寝てる時 |
例えば熱いものを手で触れたときに「熱い!」と感じるのは感覚神経が働くからです。そこで感覚神経のおかげで手から脳へ信号がいき、脳が手へ「手を引っ込めろ!」という信号が伝わるので手を曲げることが出来るのです。
交感神経は簡単に言えば活動的に動くときに働く神経で、副交感神経は休む時に働く神経です。では、これを踏まえたうえで各脳神経の働きをみてみましょう。
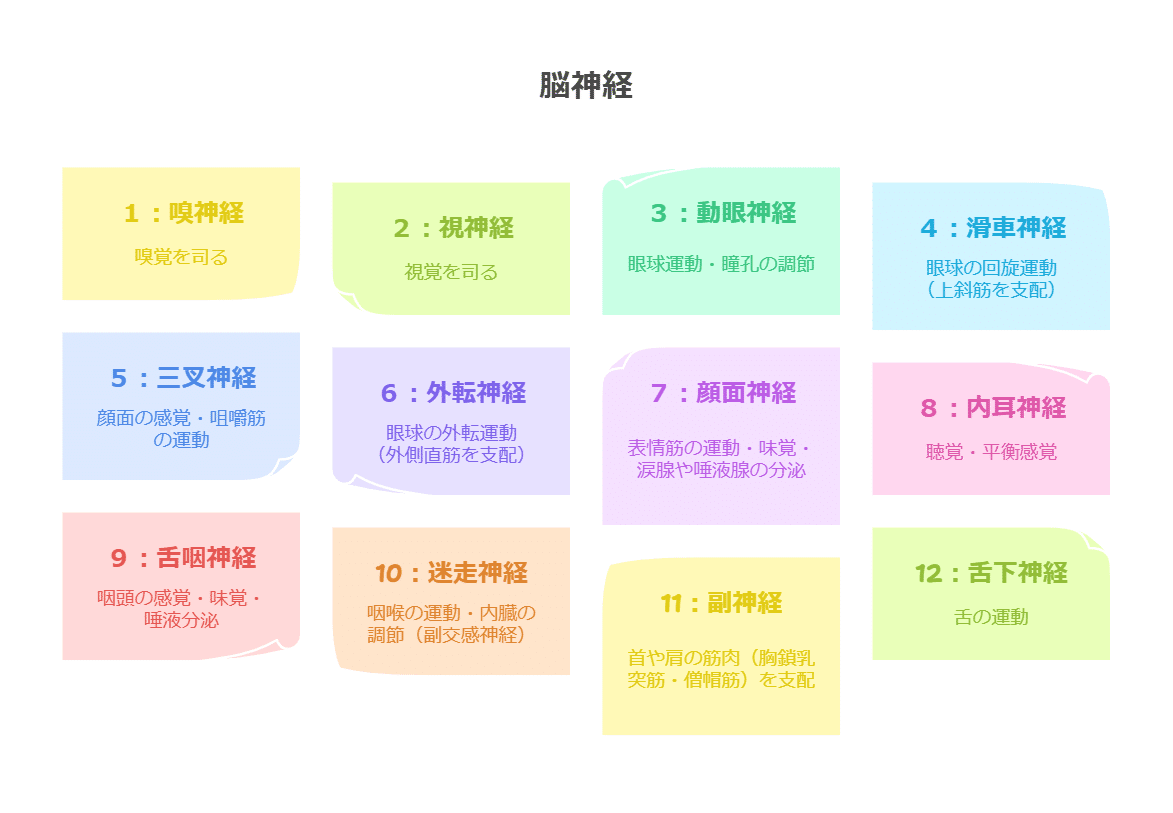
では上記までの解説をふまえて選択肢を全てみていきます。
①⇒視神経は視覚を司るもので、目を動かす神経ではないです。目を動かす神経は、動眼・滑車・外転神経などです。そのため、これは不正解ですね。
②⇒舌下神経は舌の運動を司る神経なので運動神経です。なので感覚神経ではないので不正解です。
③⇒三叉神経は顔面の感覚や咀嚼筋の運動の働きがあります。目を動かす神経は、動眼・滑車・外転神経などです。なので、これも不正解です。
④⇒内耳神経は第Ⅷ(8)脳神経なので不正解です。
⑤⇒正解
問13 排卵を誘発するホルモン
問13 解説です↓
| 部位 | ホルモン名 | 略称 | 主な働き |
|---|---|---|---|
| 前葉 | 成長ホルモン | GH | 体を大きくする。骨や筋肉の成長を助ける。 |
| 甲状腺刺激ホルモン | TSH | 甲状腺に働いて、ホルモンを出させる。 | |
| 副腎皮質刺激ホルモン | ACTH | 副腎に働いて、ストレスに関わるホルモンを出させる。 | |
| 卵胞刺激ホルモン | FSH | 卵巣や精巣に働いて、卵や精子を作るのを助ける。 | |
| 黄体形成ホルモン | LH | 排卵やホルモンの分泌をうながす。 | |
| プロラクチン | PRL | 母乳を作るのを助ける。 | |
| 後葉 | バソプレシン (抗利尿ホルモン) | ADH | 腎臓に働いて、水を体にとどめる。 |
| オキシトシン | (OT) | 子宮を収縮させる。母乳を出すのも助ける。 |
上記が下垂体から分泌される主なホルモンです。
それぞれの選択肢をみていきます↓
① ◎
②⇒性腺刺激ホルモン放出ホルモン。視床下部から分泌。
③⇒下垂体から分泌されるけど働きが違う
④⇒卵巣の黄体から分泌
⑤⇒卵巣。エストラジオールはエストロゲンのうちの1つ。
問14 交尾排卵動物
問14 解説です↓

ウサギと猫は特に有名なので覚えておきましょう。
問15 内胚葉由来
問15 解説です↓
| 器官系・部位 | 内胚葉由来の主な臓器・構造 |
|---|---|
| 消化器系(主に上皮) | 咽頭、食道、胃、小腸、大腸、直腸の上皮、肝臓、膵臓 |
| 呼吸器系 | 咽頭、喉頭、気管、気管支、肺(上皮部分) |
| 泌尿器系(部位による) | 膀胱上皮、尿道の一部 |
| 内分泌器官 | 甲状腺、上皮小体(副甲状腺)、胸腺(上皮成分) |
| その他 | 中耳腔上皮、耳管上皮、扁桃の上皮、咽頭の一部、舌の一部上皮 |
内胚葉は主に「消化管とその付属器官+呼吸器の上皮」に関わります。
胚葉とそこからできる主な臓器・組織
① 外胚葉
体の外側や神経系をつくる。
→ 皮膚(表皮、毛、爪)、口腔や肛門の一部の上皮、脳、脊髄、末梢神経、網膜、耳の内耳など。
② 中胚葉
筋肉・骨・血管・生殖・泌尿系など体の構造や循環系をつくる。
→ 筋肉、骨、軟骨、血液、心臓、血管、腎臓、尿管、生殖器(卵巣、精巣)、脾臓、結合組織、皮膚の真皮など。
③ 内胚葉
消化器・呼吸器の内側(上皮)や一部の内分泌器官をつくる。
→ 消化管(咽頭〜直腸までの上皮)、肝臓、膵臓、気管、肺(上皮)、甲状腺、上皮小体、膀胱の一部など。
問16 新生子の飼育と看護
問16 解説です↓
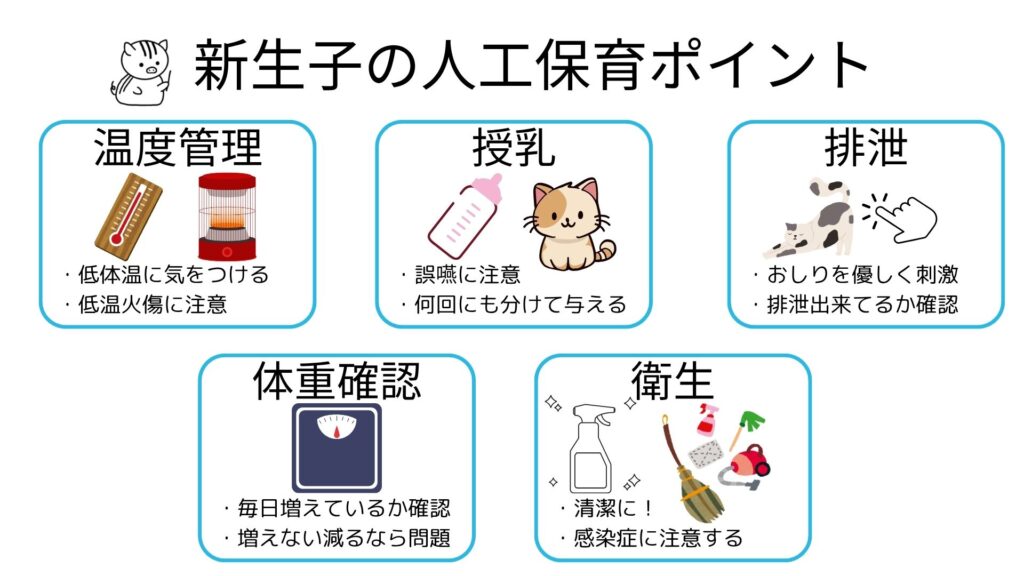
新生子保育に大事な点をまとめました↓
① 体温管理
- 新生子は体温調節が未熟。室温や保温は重要!
- 低体温(35℃以下)は危険
② 授乳・栄養管理
- 初乳は非常に重要(免疫グロブリン含有) → 出来るだけ早く摂取
- 母乳が不足/飲めない場合 → 犬猫用人工乳(哺乳瓶/シリンジ使用)
- 哺乳間隔(目安)
- 生後1週 → 2〜3時間ごと
- 生後2週 → 3〜4時間ごと
- 生後3〜4週 → 4〜6時間ごと
- 誤嚥注意 → 一度に大量に飲ませない
③ 排泄の補助
- 生後2〜4週までは自力排泄困難
- 本来は母が舐めて刺激 → 人工飼育時は飼育者が刺激(湿らせたガーゼなどで肛門・尿道口を優しく刺激)
- 排尿・排便を毎回確認
④ 体重管理
- 毎日同じ時間に体重測定(1日1〜2回)
- 毎日5〜10%増加が望ましい(目安)
- 体重が増えない/減る → 早急に対応(低栄養、疾患、感染リスクなど)
⑤ 感染予防
- 新生子は免疫が未熟
- 飼育環境は清潔に保つ(消毒、換気)
- 人の手洗い・消毒を徹底
☝観察ポイント
- 体温
- 哺乳量・回数
- 体重の推移
- 皮膚や粘膜の色(チアノーゼや貧血の有無)
- 活動性(元気がない、鳴き声が弱いなどは異常)
- 排尿・排便状況
他の選択肢についても見ておくと
①⇒6週以降が理想
②⇒毎日体重測定すべき
③⇒自分で排便出来ないので刺激をしないと命に関わる
④⇒新生子用のミルクを使うべき
⑤⇒◎
問17 維持行動
問17 解説です↓

動物の維持行動とは、生命を維持するために必要な基本的な行動のことです。
たとえば:
- 食べる(摂食行動)
- 水を飲む(飲水行動)
- 呼吸する
- 眠る・休む(睡眠・休息行動)
- 排泄する(排尿・排便行動)
- 体温を調整する(毛づくろい、日向ぼっこ、穴掘りなど)
などが含まれます。
つまり、生きるために欠かせない行動=維持行動、というイメージです。
問18 認知機能不全
問18 解説です↓
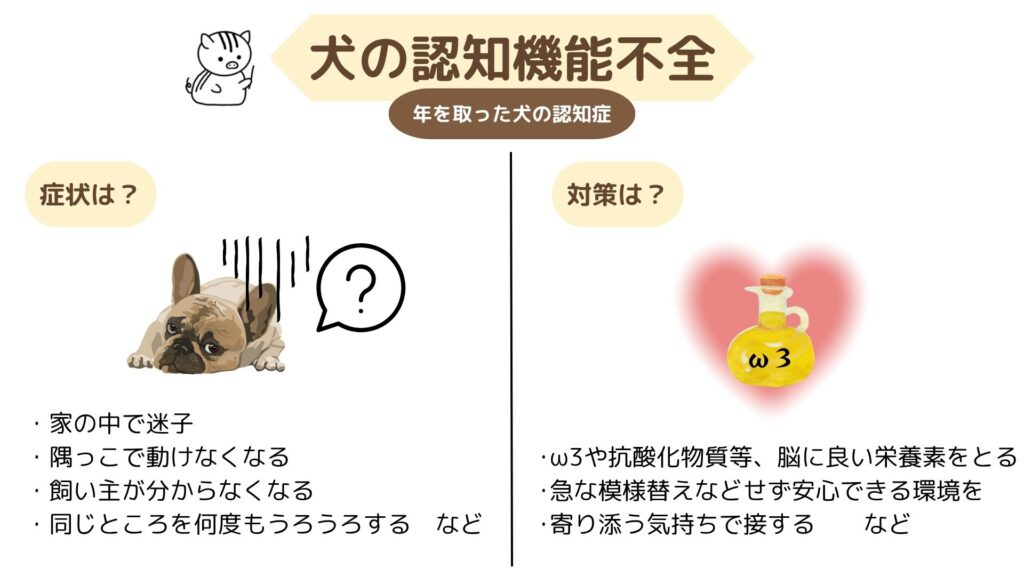
犬の認知機能不全(Cognitive Dysfunction Syndrome:CDS)とは
犬の認知機能不全症候群(CDS)は、加齢に伴い脳の機能が低下し、認知・行動・学習能力などに変化が見られる状態です。いわば犬の「認知症」にあたるもので、特に高齢犬に多く見られます。
主な症状
不安:落ち着きがなくなる、吠え続ける、不安そうな行動が増える
見当識障害:家の中で迷子になる、家具の裏に入り出られなくなる
社会的交流の変化:飼い主や他の動物との関わりに変化がみられる(無関心、攻撃的など)
睡眠と覚醒の変化:夜間に起きて鳴く、昼夜逆転する
排泄の失敗:トイレの場所を忘れる、失禁する
活動レベルの変化:無目的に歩き回る、活動量の低下
対策
この病気は完全には治せないですが、以下のような工夫をすることで進行をゆっくりにしたり、症状を軽くすることはできます。
- ω3などの栄養素が入ってるごはん(脳にいい栄養が入っている)をあげる
- 薬を使うこともある
- やさしく接して、安心できる環境をつくる
問19 ビタミン
問19 解説です↓
| ビタミン名 | 化学名・別名 | 脂溶性/水溶性 |
|---|---|---|
| ビタミンA | レチノール、レチナール、レチノイン酸 | 脂溶性 |
| ビタミンD | カルシフェロール(D2: エルゴカルシフェロール、D3: コレカルシフェロール) | 脂溶性 |
| ビタミンE | トコフェロール、トコトリエノール | 脂溶性 |
| ビタミンK | フィロキノン(K1)、メナキノン(K2) | 脂溶性 |
| ビタミンB1 | チアミン | 水溶性 |
| ビタミンB2 | リボフラビン | 水溶性 |
| ビタミンB3 | ナイアシン(ニコチン酸、ニコチンアミド) | 水溶性 |
| ビタミンB5 | パントテン酸 | 水溶性 |
| ビタミンB6 | ピリドキシン、ピリドキサール、ピリドキサミン | 水溶性 |
| ビタミンB7 | ビオチン(旧名:ビタミンH) | 水溶性 |
| ビタミンB9 | 葉酸(フォレート) | 水溶性 |
| ビタミンB12 | コバラミン (シアノコバラミンなど) | 水溶性 |
| ビタミンC | アスコルビン酸 | 水溶性 |
ビタミンB12は、体にとってとても大事なビタミンのひとつです。特に 血をつくったり、神経を健康に保ったり するのに必要です。
ビタミンB12の働き
- 赤血球を作る
→ 赤血球は体中に酸素を運ぶ働きをします。ビタミンB12が足りないと、貧血になることがあります。 - 神経を守る
→ 神経が正しく働くために必要です。足がしびれたり、ふらふらしたりするのを防ぎます。 - DNAを作る
→ 細胞が新しくなるときに使う大切な材料になります。
多く入ってる食べ物
ビタミンB12は 魚・肉・卵・乳製品 に多く含まれています。植物性の食品にはあまり入っていないので、ベジタリアンやビーガンの人は注意が必要です。
足りないと出る症状
- 貧血になる(疲れやすくなる)
- しびれやふらつきが出る
- 記憶力や集中力が落ちる
ビタミンB12は、 元気な体としっかり働く脳・神経を保つために欠かせないビタミンです。毎日の食事でしっかりととることが大切です。
問20 栄養素
問20 解説です↓
| 栄養素 | 主なはたらき | 分解されると何に変化する? |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 体をつくる(筋肉・皮ふ・内臓など) | アミノ酸 |
| 脂質(ししつ) | エネルギーになる、体を守る(脂肪のクッション)、ホルモンの材料になる | 脂肪酸 と グリセロール |
| 糖質(とうしつ) | エネルギーになる(体や脳の動く元) | ブドウ糖(グルコース) |
| 食物繊維(しょくもつせんい) | 腸(ちょう)の調子を整える、便通をよくする | 消化されにくい → 一部は短鎖脂肪酸に変化(腸内細菌によって分解)、多くはそのまま排出 |
| ビタミン | 体の調子を整える | そのまま使われる(分解というより吸収されて働く) |
| ミネラル | 骨や歯を作る、体のはたらきを助ける | そのまま使われる(イオンの形で吸収) |
炭水化物、脂質、蛋白質を3大栄養素といいます。そして炭水化物は糖質と食物繊維に分けられます。この三大栄養素は主に体のエネルギー源となります。
そのため、正解は1ですね。この問題はどの選択肢も必要な知識なので、他の選択肢もみていくと
①⇒◎
②⇒体内合成出来ないものが必須アミノ酸
③⇒エネルギー源になるのは3大栄養素
④⇒ビタミンD不足。ビタミンAは夜盲症など
⑤⇒ビタミンB1不足。亜鉛欠乏は皮膚病など。
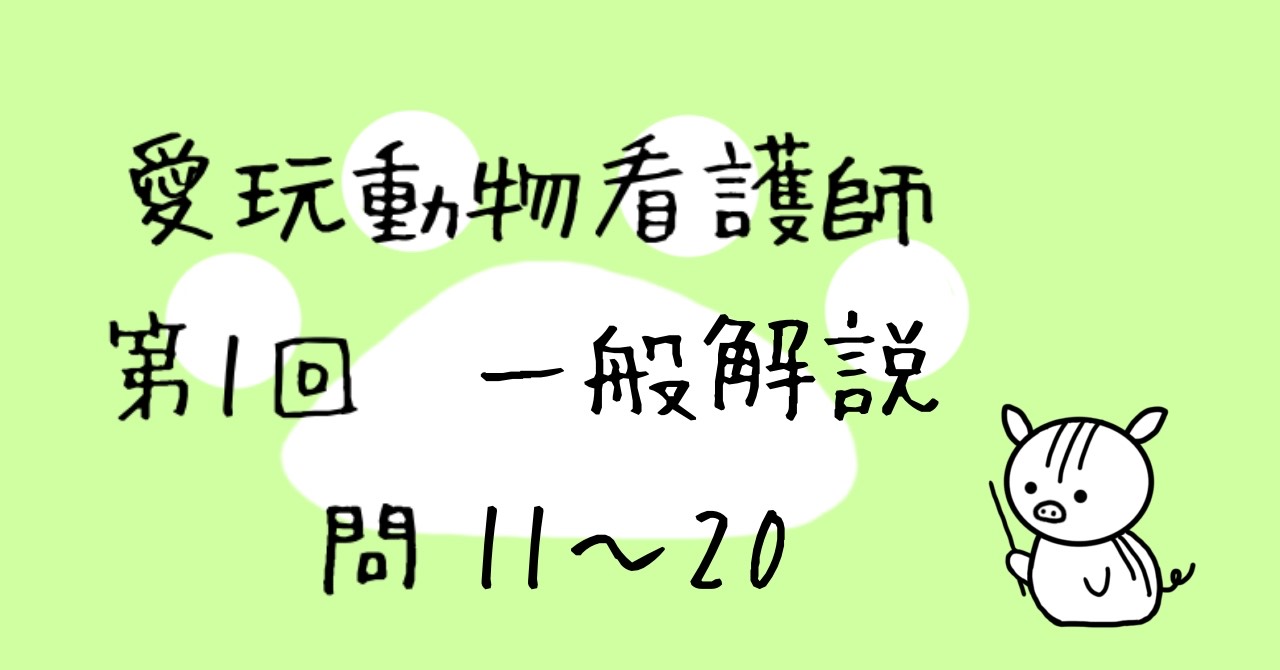
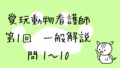
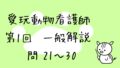
コメント